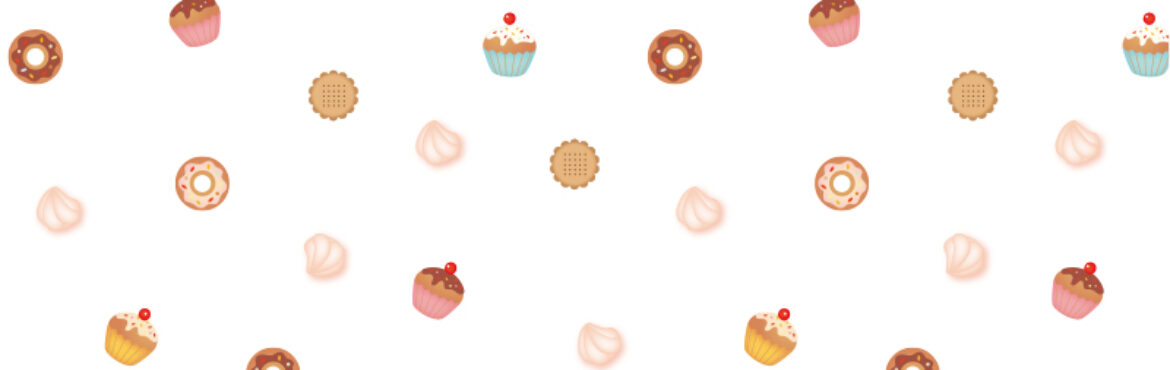
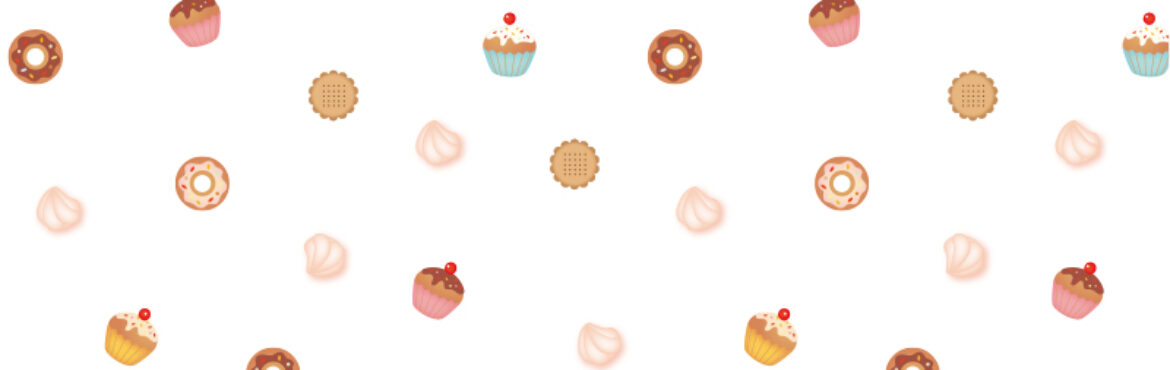
カステラといえば長崎のお菓子というイメージが強いのですが、実は岐阜県恵那市岩村町も江戸時代から伝わるカステラがおいしい町です。
長崎から遠く離れた岐阜にカステラが伝わったのは、江戸時代の寛政年間のことでした。
岩村藩の御殿医が、当時の最新の学問である蘭学を学ぶために、長崎へと留学した際に、カステラの製法を教わり、岩村に持ち帰って製法を伝えたということです。
当時は現在のように、食糧が豊かではありませんでした。
卵と砂糖をたっぷりと使ったカステラは滋養強壮に優れていたため、医師は体に良い食べ物として岩村町に伝えたのでしょう。
現在でも当時の製法を忠実に守り、当時と同じようにていねいに焼き上げられています。
カステラは、ポルトガルの宣教師が伝えた南蛮菓子です。
そのルーツは、スペインの「カスティーリャ地方」で作られていたパンだということです。
ポルトガル語では「カステラ」と発音していたため、「カステラ地方で作られていたパン」という意味でカステラと呼ばれるようになったと伝えられています。
長崎のカステラは大きな型枠に生地を流し入れて焼き上げ、その後、棒状に切り分けられます。
これに対して岩村町に伝わるカステーラは、ポルトガル人が伝えた製法そのままに、砂糖、卵、小麦粉を石臼で攪拌した生地を一つ一つ細長いケーキ型に生地を流し入れ、最初から棒状に焼き上げていきます。
このため、食パンのように側面にもこんがりと焼き目がついているのが特徴です。
ですから長崎のカステラとはまた違った味わいをしており、長崎のカステラに比べてパウンドケーキのような味わいに似ています。
素材の味がしっかりと感じられる純朴なケーキで、あっさりと食べやすく飽きることがありません。
つまり岩村町のカステーラは、本場ポルトガルの製法を忠実に受け継いだ本格的なカステラだといえるのです。
現在、岩村町には「松浦軒本店」「松浦本舗」「かめや菓子舗」の3店が、カスーテラを販売しています。
「松浦軒本店」は最も古く、寛政8年(1796年)の創業です。
もともとはこのお店が、長崎の留学から帰国した御殿医からカステラの製法を受け継ぎました。
「松浦本舗」は明治15年の創業です。
昔ながらのプレーンのほか、抹茶とブランデーも販売しており、3つの味から好みのものが選べます。
「かめや菓子舗」は、カフェが併設されているのが特徴です。
お土産としてカステーラを持ち帰りできるだけでなく、お店で本場の味を楽しむことができます。
それぞれに当時に伝わる製法を忠実に守りながらも、お店ごとに異なる特徴があります。
3軒の味の違いを食べ比べてみるのも楽しいのではないでしょうか。
Italian Restaurant Theme, Powered by WordPress